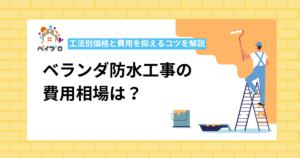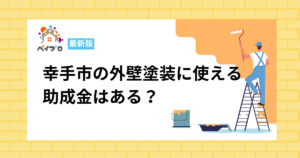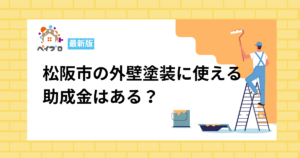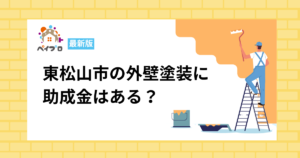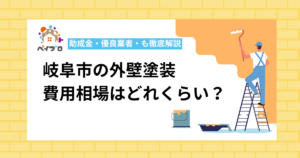住宅の美観と耐久性を保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。その中でも軒天塗装は見落とされがちですが、雨や風から家を守る重要な役割を担っています。軒天塗装の単価は様々な要因で変動するため、適正価格を知っておくことが重要です。
- 軒天塗装の単価が変動する理由と費用の内訳
- 費用を抑えるための具体的な方法と注意点
- 信頼できる塗装業者の選び方と見極め方
この記事では、軒天塗装の単価の決まり方や費用を抑えるコツ、信頼できる業者の選び方までを詳しく解説します。
\ 簡単30秒!あなたに合う塗装業者が探せる /

監修者:鹿野 博之
保有資格:中小企業診断士・宅建合格者・住環境測定士(補)など
経営改善、事業承継支援、企業研修、補助金申請支援などを得意として活動中。
軒天塗装の費用は?内訳や単価変動の仕組みを解説

軒天塗装の費用は一般的に平米単価で計算されますが、様々な要因によって金額が変動します。単価を理解して適正な価格で工事を行うために、費用内訳や変動要因について確認しましょう。
軒天塗装の単価内訳
材料費や人件費など、軒天を塗装する際の費用は、主に以下の項目で構成されています。
| 費用項目 | 内容 | 概算費用の割合 |
|---|---|---|
| 材料費 | 塗料、下地処理材など | 20〜30% |
| 人件費 | 職人の労務費 | 40〜50% |
| 足場代 | 作業に必要な足場の設置費用 | 15〜20% |
| 諸経費 | 現場管理費、一般管理費など | 10〜15% |
軒天塗装の費用は、主にこれらの要素で構成されています。特に人件費が全体の約半分を占めるため、職人の技術力や経験によって価格に差が出ます。
塗料の種類で軒天塗装単価が変動する
軒天塗装に使用する塗料の種類によって単価は大きく変わります。
| 塗料の種類 | 平米単価(目安) | 耐用年数 | 特徴 |
| アクリル塗料 | 700〜1,000円 | 3〜5年 | 低価格だが耐久性が低い |
| ウレタン塗料 | 900〜1,300円 | 5〜7年 | コストパフォーマンスが良い |
| シリコン塗料 | 1,200〜1,800円 | 7〜10年 | 耐候性に優れる |
| フッ素塗料 | 1,800〜2,500円 | 10〜15年 | 最も耐久性が高いが高価 |
塗料の選択は初期費用だけでなく、耐用年数を考慮したトータルコストで考えましょう。耐久性の高い塗料は初期費用が高くても、長期的には塗り替え回数が減るためコスト削減につながります。
軒天の素材で塗装の単価が変動する
軒天の素材によって必要な下地処理や使用する塗料が異なるため、単価も変動します。
| 軒天の素材 | 単価 (円/㎡) | 特徴・備考 |
|---|---|---|
| 木製軒天 | 1,000〜1,500 | 吸収性が高く、塗料の使用量が多くなる傾向がある。 |
| 繊維板(ハードボード) | 800〜1,200 | 比較的塗装しやすい。 |
| 金属製軒天 | 1,200〜1,800 | 下地処理が重要。専用の塗料が必要になる場合がある。 |
| 樹脂製軒天 | 900〜1,400 | 塗料の密着性を高めるための処理が必要。 |
素材によって適した塗料や施工方法が異なるため、正確な見積もりには現地での確認が必要です。
軒天の劣化状況で単価が変動する
軒天の劣化状態によって必要な下地処理の工程が増え、費用も変動します。
| 劣化状態 | 必要な処理 | 追加費用の目安 |
|---|---|---|
| 軽度の汚れ | 高圧洗浄のみ | 基本料金内 |
| 塗膜の剥がれ | ケレン作業、パテ処理 | +300〜500円/㎡ |
| カビ・藻の発生 | 殺菌・防カビ処理 | +400〜600円/㎡ |
| 腐食・腐朽 | 部分補修・交換 | +1,000〜3,000円/㎡ |
劣化が進行するほど処理工程が増え、費用も高くなります。早めのメンテナンスで大きな出費を抑えることができます。
塗装面積で単価が異なる
塗装する軒天の面積によっても単価は変動します。一般的に面積が広いほど単価は下がる傾向があります。
| 塗装面積 | 単価の目安 |
|---|---|
| 10㎡未満 | 1,500〜2,000円/㎡ |
| 10〜30㎡ | 1,200〜1,500円/㎡ |
| 30㎡以上 | 900〜1,200円/㎡ |
面積によって単価が変動する理由は、固定費(足場設置や移動費など)が広い面積に分散されるためです。小規模な塗装ほど割高になる傾向があります。
依頼する業者によって軒天塗装単価は異なる
業者によって単価設定は大きく異なります。
| 業者タイプ | 単価の特徴 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 大手塗装会社 | 高め(1,200〜2,000円/㎡) | 信頼性が高いが費用も高い |
| 中小塗装業者 | 中程度(900〜1,500円/㎡) | バランスが取れている |
| 個人事業主 | 安め(700〜1,200円/㎡) | 費用は抑えられるが品質にばらつき |
業者選びは価格だけでなく、実績や保証内容も含めて総合的に判断することが大切です。
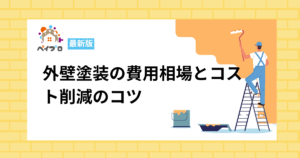
そもそも軒天塗装は必要?軒天の役割と劣化症状

軒天塗装が本当に必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。軒天の役割と劣化がもたらす影響を理解すると、適切なタイミングでメンテナンスが可能です。
軒天が持つ重要な役割
軒天は単なる見た目の要素ではなく、住宅を保護する重要な機能を持っています。
- 美観維持:外観の印象を左右する重要な部分
- 雨漏り防止:軒先から雨水が侵入するのを防ぐ
- 耐久性向上:建物内部への湿気侵入を防ぎ、木材の腐食を防止する
- 断熱・遮熱効果:屋内温度の安定に寄与する
- 小動物の侵入防止:鳥や虫などの住宅内部への侵入を防ぐ
軒天は、住宅の保護と快適性の維持に欠かせない部分です。適切な状態を保つと、住宅全体の寿命を延ばせます。
軒天の主な劣化症状
軒天の劣化は以下のような症状として現れます。
| 劣化症状 | 原因 | 放置した場合のリスク |
|---|---|---|
| 変色・色あせ | 紫外線、雨水 | 美観の低下 |
| 塗膜のひび割れ・剥がれ | 経年劣化、温度変化 | 水分侵入による腐食 |
| カビ・藻の発生 | 湿気、通気不良 | 腐食の進行、健康被害 |
| たわみ・反り | 水分侵入、構造劣化 | 構造的な問題、落下リスク |
| 腐食・腐朽 | 長期間の水分侵入 | 大規模修繕の必要性 |
上記の症状が見られたら、早めの対処が必要です。特にひび割れや塗膜の剥がれは、見た目の問題だけでなく住宅全体の耐久性に関わる重要なサインです。
軒天塗装をしない場合のリスク
軒天塗装を怠ると、塗膜が劣化して雨水が侵入しやすくなります。湿気で木部が腐食したり、カビや害虫が発生してしまいます。劣化を放置すると、塗装だけでは補えず、部材交換を伴う大掛かりな修繕が必要です。結果的に費用が膨らむうえ、外観の劣化は住宅の資産価値を下げる要因にもなります。
リスクを未然に防ぎ、長期的なコスト削減をするには、適切なタイミングで軒天の塗り替えを行うことが大切です。
失敗しない!軒天塗装の業者選びで確認すべきこと

軒天塗装を依頼する業者選びは、仕上がりの品質やコストに直結する重要なポイントです。失敗しないためにも、業者選びのポイントを確認しましょう。
複数の業者に見積もりを依頼して比較検討する
複数の業者から見積もりを取ることで、適正価格や工事内容の違いを比較できます。
見積もり依頼時のチェックポイント
- 見積書の内容は詳細に記載されているか
- 使用する塗料のメーカーや種類が明記されているか
- 下地処理や補修の範囲が明確か
- 追加費用が発生する条件が明記されているか
- 保証内容が具体的に記載されているか
単に価格の安さだけでなく、工事内容の充実度や保証内容も含めて総合的に判断しましょう。
業者の施工実績(事例)を確認する
信頼できる業者は豊富な施工実績を持っています。
確認すべきポイント
- 軒天塗装の専門的な実績があるか
- 自宅と似た条件(素材・構造)の施工例があるか
- ビフォーアフター写真が公開されているか
- 施工後の状態を確認できるか(可能であれば実際の施工物件)
実績が豊富な業者は技術力も高い傾向があります。公式サイトやSNSで、実績を確認しましょう。
保証内容とアフターフォロー体制を確認する

塗装工事を終えた後のサポート体制は、長く安心して暮らすために欠かせません。最初に、保証期間が3年から10年程度あるか確認します。
また、保証が適用される条件や、どの範囲まで修繕が行われるのかも重要なポイントです。アフターフォローでは、どのようなサービスが提供されるのかもチェックしましょう。
例えば、定期点検やメンテナンス時の対応など、実際の流れをイメージしておくと安心です。しかし、保証期間中に施工会社が廃業してしまうリスクがあります。
倒産のリスクを防ぐためにも、会社の創業年数や経営状況についても確認しておきましょう。疑問点や曖昧な表現があれば、遠慮なく業者に質問してください。
可能であれば、実際の保証書サンプルを見せてもらうと、契約内容を把握できます。
建設業許可や資格保有者が在籍しているかを確認する
適切な資格や許可を持つ業者を選ぶと、安心して工事を依頼できます。
確認すべき資格・許可
- 建設業許可(500万円以上の工事の場合は必須)
- 塗装技能士資格の保有者在籍
- 建築塗装技術管理士などの専門資格
- 職人の研修制度や技術向上への取り組み
資格情報は公式サイトで確認するか、直接問い合わせて確認しましょう。
\ 簡単30秒!あなたに合う塗装業者が探せる /
軒天塗装の費用を賢く抑えるためのコツ4つ

軒天塗装は、適切な方法で行えば、費用を抑えながら品質の高い仕上がりを実現できます。以下に、費用を抑えるためのコツを4つ紹介します。
外壁塗装や屋根塗装とセットで依頼する
軒天の塗装を外壁や屋根の塗装と同時に行うと、人件費や諸経費を抑えられます。足場の設置も一度で済むので、コスト削減になるうえ作業効率も向上します。
施工割引では、全体ではおよそ10〜20%のコスト削減が見込めます。さらに、塗り替え後の住宅全体に統一感が生まれ、仕上がりの美しさも格段にアップします。
火災保険が適用できるか確認する
台風や強風、豪雨などで軒天に損傷が生じた場合、火災保険で修理費用をカバーできる可能性があります。ただし、保険の対象となるのは風災や雹(ひょう)災、雪災など自然災害による被害のみで経年劣化は適用外です。
申請には損傷箇所の証明写真が必要です。施工業者や保険申請をサポートしてくれる専門の業者に依頼し、正確な被害状況を記録しておきましょう。
火災保険を活用すれば、自己負担を大幅に抑えられます。まずは現在の契約内容を確認し、適用条件を満たしているか確認してください。
自治体の助成金や補助金制度を利用する
地域によっては、住宅リフォームに関する多様な助成金や補助金制度が用意されています。
- 一般的な住宅リフォーム助成制度
- 省エネリフォームを対象とした補助金
- 耐震改修に伴う外装工事の補助
- 地域の景観向上を目的とした補助金など
制度を利用すると、数万円から数十万円単位の支援を受けられます。まずは、お住まいの自治体のホームページを確認するか窓口に問い合わせをしましょう。
塗装に適した春や秋に行い余計な費用発生を防ぐ
塗装工事は、気温や湿度の影響を受けやすいです。追加費用を防ぐために、適切な時期に行いましょう。
| 季節 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 春(4〜6月) | 気温・湿度が適切で塗料が乾きやすい | 花粉の影響がある |
| 秋(9〜11月) | 気温・湿度が適切で仕上がりが良い | 台風シーズンと重なる可能性 |
| 夏(7〜8月) | 乾燥が早い | 高温による塗料の不具合リスク |
| 冬(12〜3月) | 比較的工事費用が安い | 乾燥時間が長く、低温での塗装は品質低下リスク |
春や秋は、施工効率が良いため追加費用が発生しにくいです。また、閑散期(冬場)は割引キャンペーンを実施している業者もあります。
軒天塗装におすすめの塗料と選び方を解説

軒天塗装の塗料は、美観だけでなく耐久性や機能性にも大きく影響します。最適な塗料を選ぶポイントを解説します。
軒天塗装に適した塗料の種類
軒天塗装には主に4種類の塗料が使用されます。それぞれの特徴を理解して最適な選択をしましょう。
| 塗料の種類 | 特徴 | 価格帯(㎡あたり) | 耐久年数 |
|---|---|---|---|
| アクリル塗料 | 低価格、扱いやすい、通気性が良い | 700〜1,000円 | 3〜5年 |
| ウレタン塗料 | コストパフォーマンス良好、耐久性と価格のバランスが取れている | 900〜1,300円 | 5〜7年 |
| シリコン塗料 | 耐候性・耐水性に優れている、汚れにくい | 1,200〜1,800円 | 7〜10年 |
| フッ素塗料 | 最高レベルの耐久性、変色しにくい | 1,800〜2,500円 | 10〜15年 |
塗料選びは初期費用だけでなく、耐用年数も考慮してトータルコストで判断しましょう。
透湿性の高い塗料を選ぶ
軒天は外気や雨風にさらされ、湿気がこもりやすい場所です。内部結露やカビの発生を防ぐには、塗膜内の水蒸気を外へ逃がす“透湿性”に優れた塗料がおすすめ。
特に、木製の軒天では透湿性の有無が耐久性に直結します。アクリル塗料やシリコン塗料など、比較的通気性の高い製品を検討しましょう。購入時には塗料缶に「透湿性」や「通気性」と明記されているかを確認してください。
湿気対策を万全にすることで、軒天のメンテナンス頻度を減らせます。
防カビ・防藻機能付き塗料を選ぶ
軒天は、湿気や日陰の影響でカビや藻が発生しやすいです。美観を長く保つには、防カビや防藻機能付きの塗料を選びましょう。防カビなどの塗料は、微生物の繁殖を抑え日陰になる部分の汚れを防いでくれます。
シリコン系やフッ素系の製品には、防カビ機能が付加されたものが多いです。購入する際は、「防カビ」「防藻」「抗菌」といった表記を目安に選ぶと安心です。
通常の塗料より若干割高ですが、メンテナンスの頻度を抑えられるため、長期的にはトータルコストの削減につながります。
軒天の素材に合った塗料を選ぶ
軒天の素材によって最適な塗料は異なります。素材との相性を考慮して選びましょう。
| 軒天の素材 | 最適な塗料 | 理由 |
|---|---|---|
| 木製 | アクリル、ウレタン | 透湿性が高く、木材の呼吸を妨げにくい |
| 繊維板(ハードボード) | シリコン、ウレタン | 耐水性が高く、板の膨張・収縮に対応できる |
| 金属製 | フッ素、シリコン | 密着性が高く、金属の膨張・収縮に強い |
| 樹脂製 | 専用プライマー+ウレタン | 密着性を高めるプライマー処理が必要 |
素材に合わない塗料を使用すると、早期剥離や色むらの原因になります。業者に素材を確認してもらい、適切な塗料を選びましょう。
耐久年数から塗料を選ぶ
塗料を選ぶ際は、耐久年数を目安に選ぶのもおすすめです。例えば、数年以内に売却を考えている場合、アクリルやウレタン塗料が適しています。
長期間住み続ける予定がある場合は、シリコンやフッ素など耐久性に優れた塗料を選ぶと、塗り替えの頻度を減らせます。他の外装部分と同時にメンテナンスを行いたい場合は、塗り替えサイクルが同じ製品を選ぶと施工にかかる費用を抑えられます。
ライフプランに合わせた塗料を選び、無理なくメンテナンスできるようにしましょう。
予算に合わせて最適な塗料を選ぶ
塗料を選ぶ際には、予算を考慮し費用対効果を見極めます。限られた予算の場合は、コストパフォーマンスに優れたウレタン塗料がおすすめ。塗り替え回数を減らしたい場合や長期的なコスト削減を重視するなら、シリコンやフッ素塗料などを選ぶと良いでしょう。
耐久性が高い製品なので、メンテナンスの負担が減ります。また、劣化しやすい部分には高耐久塗料を塗り、その他には標準的な塗料を使用すると予算を減らせます。
軒天がおしゃれに仕上がる色

軒天の色選びは、住宅の印象を大きく左右します。おしゃれな仕上がりになる色の選び方について解説します。
白やクリーム系の色
白やクリーム系は最も一般的な軒天の色で、清潔感と明るい印象になります。
- 純白:最も清潔感があり、明るい印象を与える
- オフホワイト:柔らかな印象で多くの外壁色と調和する
- クリーム色:温かみのある印象で、ナチュラルテイストの住宅に合う
白系は汚れが目立ちやすいデメリットがありますが、軒天は比較的汚れが付きにくい場所なので人気の色です。
黒やグレー系の色
モダンな印象を与える黒やグレー系の色も、近年人気が高まっています。
- ダークグレー:洗練された印象で高級感を演出
- チャコールブラック:シャープでコントラストの強い印象
- 濃紺:黒よりも柔らかな印象で和モダンにも合う
暗色系は汚れが目立ちにくいメリットがあります。しかし、小さな空間だと圧迫感を与える可能性があります。外壁やサッシとのバランスを考慮して選びましょう。
クリア塗装
木製軒天の場合、木目を活かしたクリア塗装もおしゃれでおすすめです。
- 無色透明:木材本来の色と質感を最大限に活かせる
- 着色クリア:木目を残しながら色味を調整できる
- オイルステイン:自然な風合いで経年変化も楽しめる
クリア塗装は木の温かみを活かせますが、紫外線による変色が起きやすいです。使用する場合は、耐候性の高いクリア塗料を選びましょう。
軒天塗装をDIYで行うメリットとデメリット

軒天塗装はDIYで行うことも可能です。メリットとデメリットを理解し、自分で行うべきかプロに依頼すべきか判断しましょう。
DIYで軒天塗装するメリット
DIYで軒天を塗装すれば、業者に依頼するより費用を抑えられます。自分の都合に合わせて、休日や空き時間など好きなタイミングで作業できるのも魅力でしょう。
完成後には、自分の手で仕上げた達成感が得られ、家への愛着も一層深まります。また、塗装作業を通じて住宅メンテナンスの知識や技術が身につきます。
将来的な補修や点検にも役立つスキルを習得できます。小規模な軒天であれば、材料費や足場設置費が抑えられるため、DIYがおすすめです。
軒天塗装をDIYで行うデメリット
DIYで軒天を塗装する際は、仕上がりのムラが出やすいのがデメリットです。また、高所作業のため、転落リスクもあります。準備から片付けまで自分でしなければいけないため、労力がかかるのもデメリットといえるでしょう。
安全や塗装の保証面で不安な場合は、DIYよりも業者に依頼すると安心です。
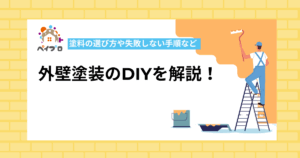
軒天塗装をDIYする際の手順

DIYで、軒天塗装に挑戦する場合の基本的な手順を解説します。安全に作業を行い、きれいに仕上げるためのポイントを押さえましょう。
DIYに必要な道具と材料を準備する
軒天塗装のDIYに必要な主な道具と材料は以下の通りです。
【必要な道具】
- 脚立または足場
- 養生テープ、養生シート
- ワイヤーブラシ、サンドペーパー
- マスキングテープ
- 刷毛、ローラー、トレイ
- 防塵マスク、ゴーグル、手袋
- 高圧洗浄機(レンタル可)
- ヘラ、パテ
【必要な材料】
- 下地処理剤(プライマー)
- 塗料(軒天用)
- パテ(必要に応じて)
- 防カビ剤(必要に応じて)
- シンナー(塗料に応じて)
事前に必要な道具と材料をすべて揃えておくことで、作業がスムーズに進みます。ホームセンターでDIY用の軒天塗装セットも販売されています。
軒天の下地処理をする
塗装を美しく長持ちさせるためには、下地処理を丁寧に行うことが大切です。最初に高圧洗浄機で表面の汚れを落とします。水圧はあえて低めに設定し、軒天を傷めないよう注意しましょう。
洗浄後は、24時間ほど乾燥させます。古くなった塗膜や浮いている部分は、ヘラやワイヤーブラシで取り除いてください。
サンドペーパー(120〜180番)があると、表面のざらつきを均一に整えられます。もし亀裂や小さな穴がある場合は、パテで補修してから、防カビ剤を使ってカビの発生を予防します。
防カビ剤の上から、プライマー(下塗り剤)を塗布すれば、新しい塗料の密着性が高まります。
養生をする

塗装前に養生をし、塗料が付着してはいけない箇所を保護しましょう。軒天と壁の境目にはマスキングテープを丁寧に貼り、塗料がはみ出すのを防ぎます。
次に、軒下の地面や周囲の植木にはビニールシートをしっかり敷き詰め、汚れをガード。雨樋や照明器具もビニールで覆っておくと、作業中の飛散を防げます。
窓や建具まわりも養生テープでカバーし、塗装範囲を明確にしておくと後片付けが楽になります。風の強い日には、養生シートが飛ばされないよう石や重しで押さえておきましょう。
養生は作業の手間を省くためではなく、仕上がりを美しく保つための大切な工程です。
軒天の塗装を行う
実際の塗装作業は以下の手順で行います。塗料をよく攪拌する(缶の底に沈殿している成分を均一にする)
- 角や端部など細かい部分を刷毛で塗る(カットイン)
- 平面部分をローラーで塗装する
- 1回目の塗装を乾燥させる(塗料の指定時間を厳守)
- 2回目の塗装を行う(1回目と直角方向に塗ると均一になる)
- 完全に乾燥させる
塗料は薄く均一に塗ることがポイントです。厚塗りすると乾燥不良やたれの原因になります。また、気温や湿度に応じて塗料の粘度を調整することも重要です。
軒天塗装をDIYする場合の注意点

DIYで軒天塗装を行う際には、以下の点に特に注意して作業を進めましょう。
高所作業は安全に行う
軒天塗装は高所作業のため、安全対策を最優先に考えましょう。安定した脚立や足場を使用し、必ず脚立を完全に開き平らな場所に設置します。
不安定な場所への設置は避け、補助者に支えてもらうと安心です。転倒時の衝撃を和らげるため、ヘルメットの着用も検討しましょう。
長時間の作業や疲労を感じた場合はこまめに休憩を取ってください。雨天や強風時は、無理に作業を進めず、別の日に延期しましょう。
電線の近くでの作業は感電のリスクが高いため、細心の注意が必要です。無理な姿勢での作業は、事故につながる恐れがあります。
作業中は必要に応じて足場の位置を変え、常に身体に負担のかからない姿勢を心がけてください。
ムラや刷毛後が残らないようにする
塗装のムラや刷毛後を防ぐためには、塗料の粘度を希釈率に合わせて調整し、適切な「ぬれ感」を保ちながら作業します。
一度に広い面積を塗ろうとせず、1~2㎡ずつ区切ってローラーや刷毛を動かしましょう。塗りすぎによる、厚みムラを防ぎます。ローラーは一定方向に動かし、仕上げは軽く一方向に流すと、塗膜が均一になります。
重ね塗りは、前の塗装が完全に乾く前に行うと境目が目立ちにくくなります。刷毛跡が気になる場合は、半乾きのタイミングで軽く刷毛を引き、余分な塗料をならします。
均一な仕上がりを目指し、塗り具合と乾燥具合を確認しながら進めてください。
塗装後の乾燥時間を守る

塗料の性能を最大限に引き出すために、缶に記載された乾燥時間を守りましょう。気温や湿度によって乾燥速度は変わるため、低温や高湿度の環境では記載時間より長めに乾燥させます。
表面が乾いていても、内部は硬化していないことがあります。次の重ね塗りは、前塗装が完全に乾いてから行ってください。最終塗装後は、少なくとも24時間は雨に当てないよう管理しましょう。
乾燥不足で次の工程に進んでしまうと、塗膜の剥がれや変色を招く原因になります。塗装作業の最後まで十分な乾燥時間を確保することが重要です。
軒天の劣化が激しい場合は業者に依頼する
軒天の劣化が激しい場合は、専門業者への依頼を検討しましょう。軒天の劣化が進んでいると、塗装だけでなく部材の交換や構造補修が必要です。無理に塗装はせず、専門業者に依頼し欠陥を大きくしないよう注意してください。
\ 簡単30秒!あなたに合う塗装業者が探せる /
軒天塗装で押さえておくべき重要ポイント

軒天塗装を成功させるための重要なポイントをまとめました。軒天の塗装を検討している方は、参考にしてください。
塗装前に軒天の劣化状態を正確に診断する
軒天の塗装をする前に、劣化状態を確認します。目視で、塗膜の剥がれや変色など表面の劣化を確認し、打診検査で空洞化などがないかチェックします。
湿気やカビの発生状況、軒天材のたわみ、反りなども点検しましょう。診断に基づいて、最適な処置や塗装計画を立てると、軒天を長持ちさせられます。
軒天の素材と状態に最適な塗料や工法を選ぶ
木製の軒天は通気性と防カビ性を重視し、金属製の場合は防錆処理を行ったうえで密着性の高い塗料を選びます。樹脂製は専用プライマーを塗布し、素材に合った塗料を使用しましょう。
劣化が進んでいる場合は、塗装前に下地補強や部分的な交換を行うと、仕上がりの耐久性と美観が向上します。素材や状態に合わせた塗料と施工方法を選び、塗装を長持ちさせましょう。
定期的な点検とメンテナンスで軒天の寿命を延ばす
軒天の長寿命化には、定期的な点検と早めの対応が大切です。
- 年に1〜2回の目視点検を習慣化
- 雨漏りや台風後は特に注意して点検
- 小さな劣化兆候(わずかな塗膜剥がれなど)を見逃さない
- 5〜7年ごとに専門家による点検を受ける
- 必要に応じて部分的な補修を行う
早期発見や早期対応が大規模修繕を防ぎ、結果的にコスト削減につながります。
軒天塗装に関するよくある質問(Q&A)

軒天塗装に関して、よくある質問と回答をまとめました。疑問解消の参考にしてください。
軒天塗装の単価を把握し適正価格で施工しよう

軒天塗装の単価は、素材や塗料などの条件によって異なります。しかし、塗料や劣化状況などを把握しておくと、適正な価格で施工が可能です。軒天は家の印象を左右し、建物を保護する大切な部分です。適切な塗装で長持ちさせましょう。
ペイプロでは、優良塗装業者を無料でご紹介しています。まずはお気軽にご相談ください。